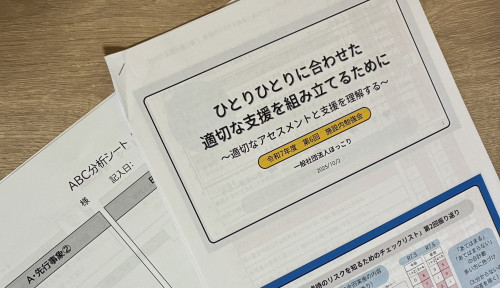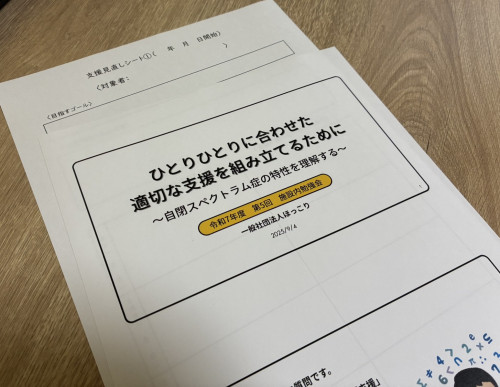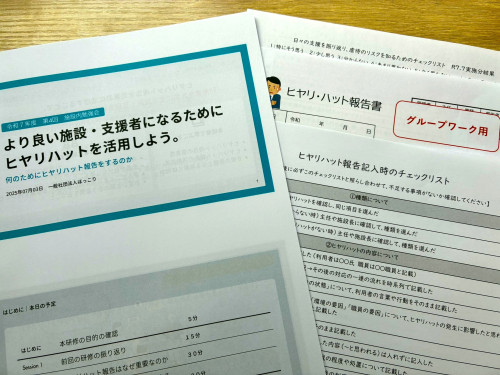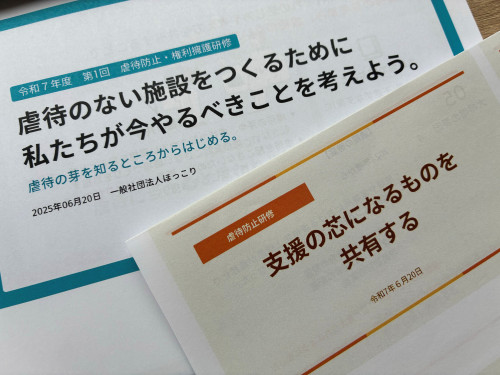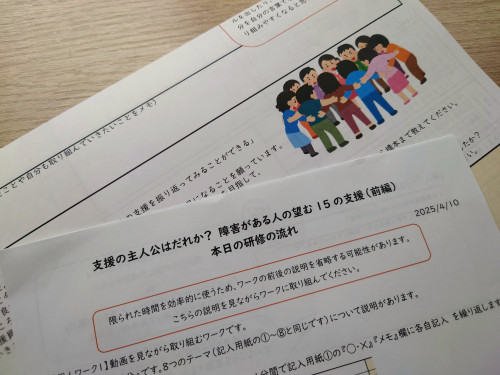職員勉強会
◆施設内勉強会◆
一般社団法人ほっこりでは、支援力向上を目指し
今年度より職員勉強会を年に10回開催することになりました。
勉強会・研修担当は、生活支援センターここの相談員です。
ーーーーーーーーー第6回ーーーーーーーーー
10月2日(木)第6回の勉強会を実施しました。
今回のテーマは
「ひとりひとりに合わせた適切な支援を組み立てるために
~適切なアセスメントと支援を理解する~」でした。
今回は、イギリスの自閉症協会が提唱する
自閉スペクトラム症の支援のための5つの基本原則「SPELL」をベースに、
アセスメントや構造化、氷山モデル、ABC分析など、
支援をするうえで欠かせない幅広い内容を全員で勉強しました。
研修の中で気になったところや、もっと知りたいと思ったところを
各自で学び理解を深めていきたいと思います。
研修の最後には、2グループに分かれて「ABC分析シート」を使った
事例検討のグループワークをしました。
初めてABC分析に触れる職員も多かったですが、質問を繰り返すことで
理解を深めながらABC分析の方法を学ぶことができました。
ツールは何度も使うことで、上手く使えるようになると思います。
今回限りで終わらせず、これからも必要に応じてツールを活用し、
より良い支援を目指していきたいです。
次回は11月です。虐待防止や権利擁護に関する研修を実施予定です。
年10回を予定していた施設内勉強会も、折り返しを迎えました。
これからも、少しでもほっこりの支援が向上していくよう、
研修に取り組んでいきたいと思います。
ーーーーーーーーー第5回ーーーーーーーーー
9月4日(木)第5回の勉強会を実施しました。
今回のテーマは
「ひとりひとりに合わせた適切な支援を組み立てるために
~自閉スペクトラム症の特性を理解する~」でした。
9月・10月の施設内勉強会にて、
障害特性・アセスメント・支援の組み立てまでの一連の流れに関する
勉強を再度行い、職員みんなでより良い支援とは何なのかを考える予定です。
今回は、障害全般に関する勉強と、自閉スペクトラム症の障害特性に関する勉強を
行いました。障害特性がかなり幅広く、限られた時間の中では伝えきれない部分も
あったと思いますが、職員それぞれが気になることを深めていってもらえればと
思っています。
そして勉強会の最後には、「支援見直しシート」を用いて
特定の利用者を対象に、「目指すゴール」や「支援の方法」を考える
グループワークを行いました。
具体的な目標を立てることが少し難しかったですが、今回のことをきっかけに
支援の方法を考える→実際にやってみる→振り返って改善する→やってみる…という
サイクルが定着するよう、全職員で取り組みを進めていきます。
次回、10月はアセスメントや支援に関する勉強を行い、
さらに知識や技術を高めていきたいと思います。
研修の限られた時間だけでは完璧に理解して取り組むことは難しいかもしれません。
各自、研修で学んだことを1つでも支援の中で実践して
学んだ知識や技術が自分のものにできるよう努めていきたいです。
ーーーーーーーーー第4回ーーーーーーーーー
7月3日(木)第4回目の勉強会を実施しました。
今回のテーマは「ヒヤリハットの適切な活用について」です。
ヒヤリハット報告は何を目的に行うのか、
ヒヤリハット報告書は、どのようなことに気をつけて書くべきかということを
職員全体で再度確認し、ある1つの事例について、
全員で原因や問題点、再発防止策を考えるグループワークを実施しました。
また、研修前に「虐待のリスクを知るためのチェックリスト」を
全職員に実施し、その結果を通して見えてきた施設の課題を全員で確認しました。
「尊厳のある生活」「合理的配慮」といった言葉についても、
各々の考えを共有する中で、大切にすべきことは何なのかを
改めて確認できたと思います。
研修の最後には「にやりほっと」を取り上げました。
「利用者の笑顔が増える施設づくり」
「安心して通える安全な施設づくり」のために、
良いところに気づき、そして課題にも、気づくことができる
そんな職員になることを目指して、これからも
取組みを進めていこうと思います。
8月は施設内勉強会をお休みして、
次回は9月の実施を予定しています。
施設内勉強会を繰り返すことで、
勉強する→実践する のサイクルが習慣化することを
目指していきたいと思います。
ーーーーーーーーー第3回ーーーーーーーーー
6月20日(金)第3回目の勉強会を、虐待防止研修と合わせて実施しました。
第1部「支援の芯になるものを共有する」
第2部「虐待のない施設をつくるために私たちが今やるべきことを考えよう」の
2部構成で、それぞれほっこり施設長・ここ相談員が担当しました。
第1部では、虐待件数が全国的に増えていること、そして施設の現状に触れ、
支援の基本となる「職員行動規範」を再度確認しました。
第2部では、「虐待の芽を知る」ことを目的としたグループワークを実施しました。
ふせんと模造紙を使うワークは、あまり職員にはなじみがないようでしたが、
グループで協力して取り組むことが出来ました。
研修全体を通しての感想を職員全員に発表してもらいましたが、
「虐待の芽がかなり身近にあること」に気づいた職員や、
「尊厳の意味を再確認できた」という職員もおり、
当たり前のこと、だけど、なかなか普段確認する機会が少ないことを
みんなでもう一度確認する良い機会になったのではないかと思います。
利用者のみなさんが、笑顔で、その人らしく通い続けられる
そんな施設であるために、これからも職員一同学びを深めていきたいと思います。
次回は7月3日にヒヤリハットに関する研修を実施する予定です。
勉強会がその1回きりで終わるのではなく、職員一人ひとりが
常に何かを吸収して、支援に活かせることを目指して、
勉強会をこれからも続けていきます。
ーーーーーーーーー第2回ーーーーーーーーー
連休明けの5月8日、第2回目の勉強会を実施しました。
今回も、特定非営利活動法人サポートひろがりの山田由美子さんの
オンデマンドセミナー動画を使用して実施しました。
テーマは『支援の主人公はだれか?~障害のある人の望む15の支援(後編)』です。
今回も前回と同じく、動画を視聴後グループワークを行い、
日頃の支援を振り返り『5月の支援の目標』を一人ひとり発表しました。
前回の勉強会よりも、より具体的な場面を想定した目標を立てていたり、
今回の勉強会を通して見つけた課題をもとに目標を作ったりと、
一人ひとりが自分と向き合う時間を持つことができました。
次回は、虐待防止に関する勉強会を6月に実施予定です。
勉強会が全職員にとって実りある時間となるよう、丁寧に準備を進めていこうと思います。
ーーーーーーーーー第1回ーーーーーーーーー
記念すべき第1回目となった4月10日は、
特定非営利活動法人サポートひろがりの山田由美子さんの
オンデマンドセミナー動画を使用して実施しました。
テーマは『支援の主人公はだれか?~障害のある人の望む15の支援(前編)』です☆彡
研修動画を視聴したあとは、約30分間で
日々の支援を振り返る個人ワークとグループワークに取り組みました。
グループワークでは、それぞれの支援について
「こんなところが良いと思ってるよ」「ここはもっとこうしてほしい!」
と全職員でざっくばらんに、意見交換をしました。
研修の最後に、研修やワークを通して見つけた課題や
もっと伸ばしていきたいところを踏まえて
4月の支援に関する目標を一人ひとり発表してもらいました。
こういった時間を作って話をすることで
支援に関するさまざまな思いや、その中で大切にしていることを
改めて聞くことができ、一人ひとりの思いを知る良いきっかけになりました。
お互いの目標を意識しながら、より良い支援ができるよう
これからも職員みんなで取り組んでいきたいと思います。
次回は5月に、『支援の主人公はだれか?~障害のある人の望む15の支援(後編)』を
テーマに勉強会を実施する予定です。
今回の勉強会を通して、見つけた改善点を活かし、
より実りのある勉強会を目指していきたいと思います。